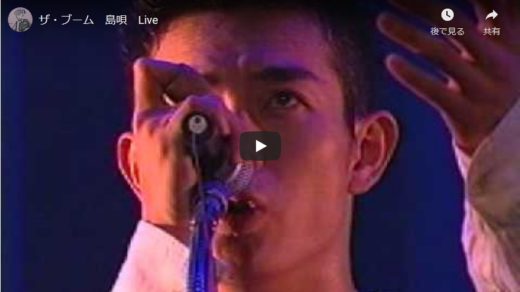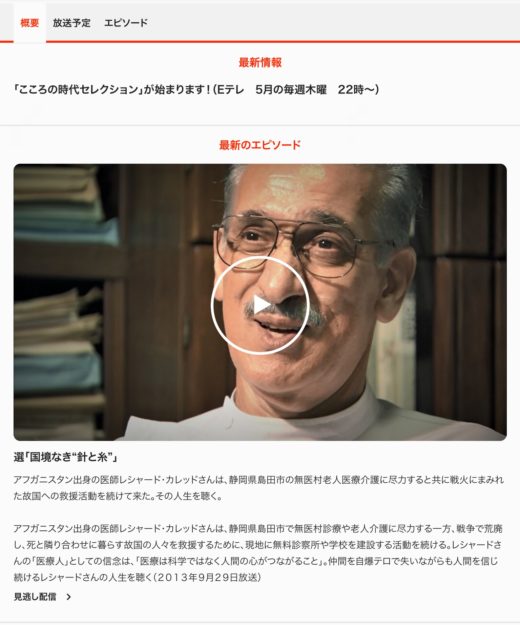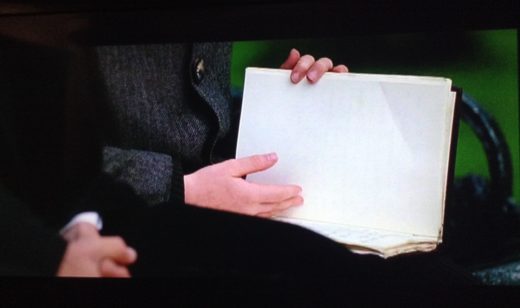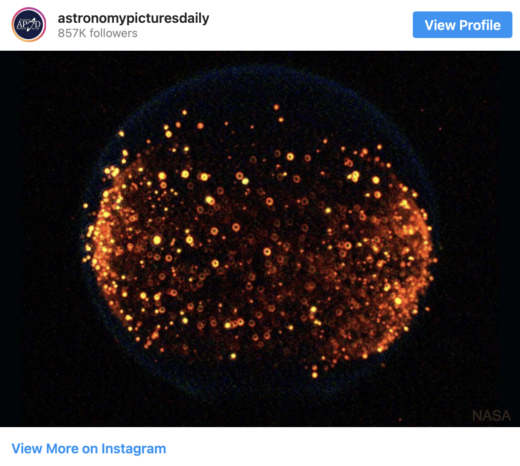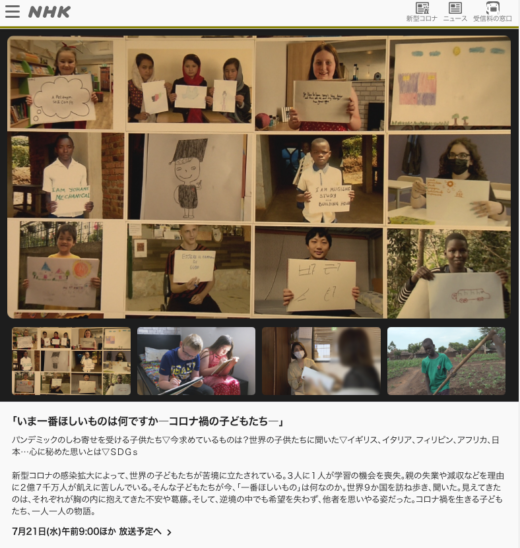手を引いて連れ出す胆力?何から?
争いに誘う磁場(空虚さ、肥大化した自我、歴史の禍根による痛み、焦り)から。
ビーレエションシップのテーマのひとつに、鍛えられた母性があります。
母性や女性性は、女性の内面だけに宿るものではなく、あらゆるジェンダーの中に宿る人間の性質として捉えています。
危険な状況で「何を最優先させるか」と問われて、「それは、人の命」と答えることを、防衛本能の女性性としたとき、
それができることは、祈ることだけでしょうか?
私たちはそれは違うと思っています。
胆力が動くとき
学校でいじめの現場に出くわした教師
例えば、学校の先生が廊下を歩いていると、一人の生徒が複数の生徒に囲まれているのを見かけた、とします。
先生が「何をやっているんだ?」と声をかけると、
複数の生徒は「みんなで遊んでいるだけです」と、囲んでいる生徒の肩を組みながら答えます。
しかし、囲まれている生徒は萎縮しているように見えます。
このとき教師はどうすべきでしょうか。
「大丈夫か?」「早く帰れよ」と声をかけて、自分はその場を立ち去ることでしょうか。
それは違うと、蜂はかつて習いました。
教師がすべきことは、声をかけてその場を立ち去ることではなく、
囲まれている生徒の手を取って、その場から必ず連れ出すことだ、と教えられました。
(それを教えてくれた先生の気迫に感じるものがあったので、すごくよく覚えています。)
教師が囲まれている生徒の手を引いてその場を連れ出すことは、
囲まれている生徒と囲っている生徒の境界線を(一時的にでも)きちんと引き直す作業であり、
周りの生徒に、ここで何が起きているのかを教師は気づいている、という明確なメッセージを伝えることになります。
このとき教師に求められるのは、機転かもしれません。
いじめが疑われるが決めつけられない場合、
囲まれている生徒を連れ出すための明確な理由が、とっさに必要になるかもしれません。
とっさの判断には、心が動いていることが必要となり、
その先生が、普段どれだけ生徒との人間関係や、自分自身との関係を作っているか、にかかっているかもしれません。
商店街で女子高生が囲まれている場面に遭遇した平次
(手前味噌なのは重々承知ですが、このとき起こった出来事を一緒にたどって読んでいただけたらと思います。)
平次は40代の頃に人生で一度だけ、高校生の女の子が囲まれているのを助けたことがあります。
地元の商店街で蜂の兄弟を連れて買い物をしているとき、
制服を着た一人の女子高生が、髪を染めた複数の女の子に囲まれているのを見かけました。
様子をうかがっていると、女子高生が髪を染めた女の子にぶつかったようで、
謝っても許してもらえずに因縁をつけられていたようです。
平次が商店街の周りを見渡すと、大人も通っているのに誰も助けようと
平次はスコンと竹を割ったような性格です。
蜂の兄弟を平次の見える範囲で一番遠くに立たせて、絶対にその場を動かな
揉め事の中に一人で入って行きました。
「震えながら謝っているのに許せないなら、警察に行こう」と全員に伝えると、
髪を染めた女の子達は、平次に何かを言いながら立ち去ったそうです。
高校生の女の子に「今のうちに早く家に帰りなさい」と言っ
彼女たちは今度は、自転車に乗っていた別の高校生の女
(30代の今の蜂が思うのは、もし
同世代の女の子達に対して、いらだちか何かを感じていたのかもしれないな、と想像しています。)
マイケルに一晩の寝る場所を差し出すことを即断したリー・アン・チューイ
蜂の好きな映画の一つに、サンドラ・ブロック主演の「しあわせの隠れ場所」という映画があります。
-
「しあわせの隠れ場所」(“The Bind Side”) 予告編
サンドラ・ブロックが演じるリー・アン・チューイは、
夜道を雨に濡れながら、一晩過ごすための体育館へ向かうマイケル・オアーに気づき、
車から降りて、「今夜泊まる場所はあるのか」とたずねます。
「泊まる場所はある」と強がるマイケルの様子から嘘を見抜き、
その場の即断で、一晩の宿として、リー・アン一家に迎えます。
ところがリー・アンは、マイケルが息子と同じ学校の生徒、ということしか知らないため、
夜の間に何も盗まれていないだろうか、という不安がふと頭をもたげます。
困っているように見える人に声をかけることは、簡単なことではありません。
(蜂も何度も気づきながらできなかったことがあります。)
その後どうすればいいだろう、という不安がよぎるからです。
リー・アンは、その瞬間瞬間に必要なことをたずね、できることをし、
孤独で、恵まれているとは言えない環境から、マイケルを連れ出すことになります。
踏切を渡り切れないおばあさんに出会った蜂
(またも手前味噌なのはわかっているのですが、
蜂のこれまでの人生で一度だけ起こった出来事を、一緒にたどって読んでいただけたらと思います。)
ある日、蜂は踏切を急いで渡っていました。
4本のレールが並ぶその踏切は、渡り終える前に、遮断機が下りることで知られている場所です。
蜂は、踏切の真ん中より手前あたりで、おばあさんを追い越しました。
そのときに、
“(おばあさんは手押し車を押しながら)ゆっくり歩いているけど、渡り切れたらいいな…”
と心配になっていました。
その心配を踏切は見透かしたかのように、
蜂がおばあさんを追い越して、2歩進んだときに、踏切の音が鳴り始めました。
”うそっ…”
嫌な予感が本当になったことに青ざめながら、
蜂はとっさにおばあさんの方を振り向き、
「手押し車を持つから、一緒に渡りましょう」と声をかけました。
するとおばあさんは、「手押し車がないと歩けない」と言うではありませんか…!
歩く支えの手押し車を知らない人に取られたら、おばあさんにとって恐怖以外の何物でもないと思った蜂は、おばあさんの横に並んで歩き始めました。
渡り終えるまで蜂の頭の中は、
列車がどちらの方向から来るのか、
万が一列車が来たときは、おばあさんを抱えて、列車が来ないレールへ移動して待とう、
とそれだけを思っていました。
向こう側には、遮断機を上げて待ってくれている男性が見えて、
”あともうちょっと”と思いながらも、(高校生の頃に、ムカデ競争の先頭だったときに気をそらして、大コケした経験があるので)それは見ないようにして、
おばあさんの足取りに合わせ、
列車が通る数秒前に、踏切を渡り終えました。
蜂の心臓はバクバクしていて(思い出している今もなのですが)、
早くその場を離れたくて、軽く話をした後に、早足で立ち去りました。
遮断機を上げてくれていた男性に会釈をしただけになってしまったのが、今でも心残りなのですが、
とっさにあの行動をしたのは、あのおばあさんが伊都に見えたからだろうと思います。
少年の命がけのデモへの参加を止めたアメリカの男性
2020年5月下旬にジョージ・フロイドさんが、白人警察官デレク・ショーヴィンによる取り締まり中に、首の圧迫で殺害された事件が起き、
世界中がその一瞬一瞬をとらえた映像を目撃することとなり、各地でデモが起こりました。
暴動や略奪が起きたり、平和的なデモが起きたり、
警官が市民に連帯の意志を見せるために地面に膝をついたり、警察解体論議へと発展したり、
今も様々なことが起きています。
その中でも、何よりも命を大事に考えて行動を起こした人たちがいました。
三世代に渡って、アフリカ系アメリカ人への差別がなくなっていないことに心底怒りながらも、
16歳の少年に「命を無駄にするな。今のやり方ではダメだ。新しいやり方を考えろ」と、
涙ながらに諭す男性の話を聞いた方も多いのではないでしょうか。
現在アメリカで起きている暴動に、黒人は必ずしも賛同しているわけじゃない。むしろ彼らの多くはもっと「マシな方法」を模索しようとしている。
悲劇を止めるのは暴動じゃない。#BlackLivesMatter pic.twitter.com/ohBURhDxjn
— LiT|翻訳キュレーター (@LiT_Japan) June 1, 2020
説得している男性は、かつては怒りに燃えて命も顧みなかったはずです。
だけど子どももいる今は、自分の身を守らなければならないし、
これまでのやり方ではうまくいかないことも、身を持って感じています。
アフリカ系アメリカ人への差別をなくすことはあきらめない、
だけど命を簡単に捨てるな、と説得する姿は、
本当に16歳の少年の身を案じて心底怒り、身を呈して止めてくれている、”肝っ玉母さん”のように見えます。
集団暴行されていた極右派の男性を救出したパトリック・ハッチンソンさん
ロンドンのウォータールー駅近くで、
アフリカにルーツを持つ人々への差別反対デモに反対していた極右派の男性が集団暴行にあう事件が起き、
普段はパーソナルトレーナーとして働いているパトリック・ハッチンソンさんがその中に割って入り、
男性を肩に担いで、危険な場から連れ出したというニュースがありました。

-
BBC NEWS JAPANよりスクリーンショット
「死者が出るのを防いだ」 ロンドンで白人男性を担ぎ助けた男性
極右派の白人男性は、アフリカにルーツを持つ人々への差別をよしとする立場の人です。
ところが彼は集団暴行に遭い、差別にあってもいいと思っていたはずの人に助け出されています。
報道写真とはすごいなと思うのですが、この写真一枚からたくさんのことが伝わってくる気がします。
パトリック・ハッチンソンさんはただ危険な目にあっている命を前にして、
「何も考えていなかった。全てを守ろうとした」と話していて、
彼の無心でどこか落ち着いた表情からは、行動と言葉に1mmのズレもないことが感じとれます。
助けている相手が、アフリカにルーツをもつ人は差別にあってもかまわない、と主張する人であっても、です。
(BBC NEWSには、パトリック・ハッチンソンさんのインタビュー動画があります。)
その一方で、極右派の白人男性は顔が真っ赤で、
何が起きているかわからない、といった混乱に満ちた表情をしていて、
パトリック・ハッチンソンさんの表情とは対照的だなと感じます。
担がれて助け出されているときでさえ、極右派の白人男性は攻撃されそうになっていたそうですが、
ハッチンソンさんの仲間がその周りを囲ってバリアを作り、攻撃できないようにしたそうです。
本当の強さとはどこにあるのかを考えせられる気がします。
なぜ胆力が動くのか: 危機回避の共通項
こうして見ていくうちに、危機的状況で何が最も力を発揮するのかと考えると、
どうも小手先の方法にはないのではないか、と思えてきます。
(もちろん危機的状況になる前に、
過去の事例を当たって(いじめ、事故、戦争(例えば自分事として考えると、真珠湾攻撃に至った理由)など)、
それがなぜ起きたのかを、自分の体で咀嚼し、
小さな変化が起きた時に、即座に、適切な方法で手を打っておくことが一番大切なことだと思っています。)
どの例にも共通しているのは、
考えたり頼まれたからしたものではなく、気がついたら勝手に体が動いていた、ということです。
勝手に体が動くというのは、自分はできると頭よりも体が速く判断しているということだろうと思います。
それはもはや、武道場外での武道のようなものかもしれません。
ただし戦う相手は、人間ではなく危機的状況で、
少ないエネルギーで、最短にこの危機的状況を切り抜けるためには、
どこをどう通ればいいのか、何をどうすればいいのか、わかっている状態と言えるかもしれません。
仮にその状態に持っていくとした場合、何をどうすればいいのでしょうか。
何をどうすればいいかわかっているというのは、自分の持つ力を理解していることとつながっているのかもしれません。
教師は、生徒より一般的には立場の強さがあります。
平次は、女子高生たちよりも年上で、社会の仕組みの中で、何をどうすればいいかわかっていました。
リー・アン・チューイは、夫婦ともに実業家で経済力があり、人の成長を支える志がありました。
蜂は、おばあさんよりも体力があって、踏切の様子を見渡す力がありました。
デモへの参加を止めたアメリカ人男性は、世代をまたいで同じテーマがどのように扱われてきたかを理解していました。
パトリック・ハッチソンさんは、パーソナルトレーナーであることから、普段から筋肉を鍛え、体の使い方を熟知していただろうと想像できます。
人によって持つ力や自然にできることが違うことに気づくと、
一人の偉大なリーダーは機能しないということが、すっと腹に落ちてくる気がします。
敵は外にいて、助けてくれる英雄も外にいると思いがちですが、
その瞬間瞬間の危機を助ける役割は、実はみんなの間を巡っていて、
次の瞬間はあなたかもしれないし、私かもしれないと思うと、ちょっとドキドキしてきます。
(この流れは、マライア・キャリーのヒーローを蜂に思い出させます。)
蜂はこれまで、「守る」ということはどういうことなのかを考えては、かき消してきました。
ひとまず今、自分なりにこれが守る方法なのかもしれないと思ったとき、
ようやく力が抜けて、深い呼吸ができるようになっています。