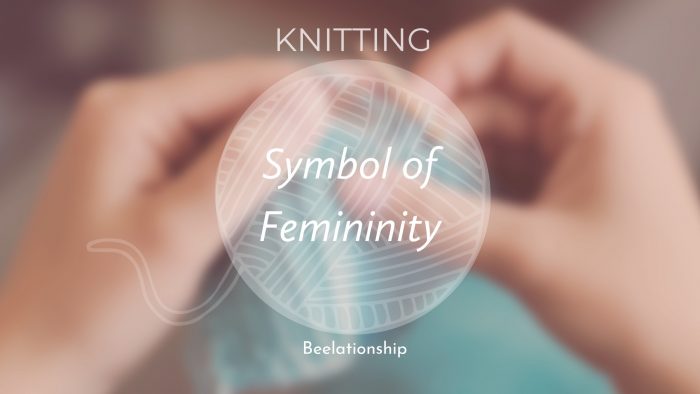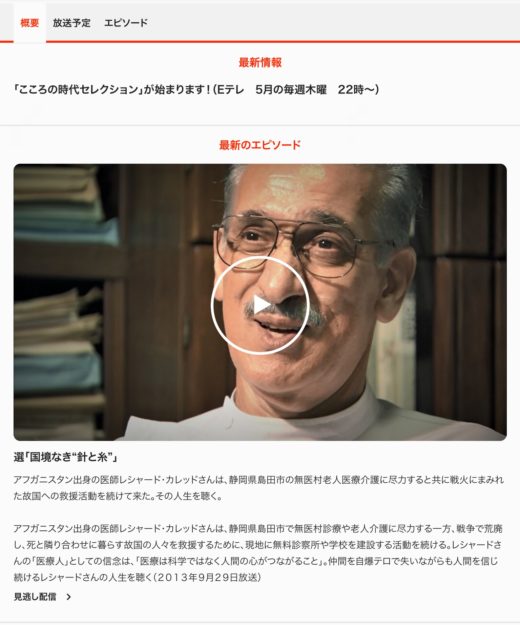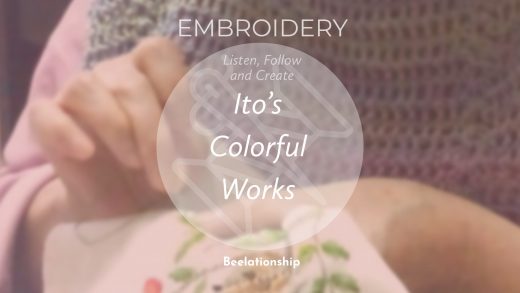手編み
編み物は、いつも3人の女性(伊都・平次・蜂)の近くにありました。
今も3人で編み物会をしていて、伊都が指南役となり、平次や蜂に編み方や製図方法を教えています。
これまでにセーター、カーディガン、ベスト、手袋、帽子などを編んできました。
編み物の世界は奥深く、間違えたり、想像と出来上がりの印象が違って、ほどくこともよくあります。
体を使わない作業に思えても、体を鍛えて、整えておくことも、実は大切です。
ずっと同じ姿勢をしていると体が硬くなりますし、指を動かし続けると、肩がこったり、腱鞘炎になったりすることがあるためです。
そうなる前に体をほぐしたり、適度に休みをとることが必要になります。
また、体に無理のない姿勢で座り続けるためにも、体幹が必要なので、体を日々動かして鍛えておくことも、大切なことなのです。
3人の手編みの歴史
編み物って静かに座ってするものじゃないの?と、毛糸のふわふわした雰囲気を覆す現実にもかかわらず、
編み物が続いているのはどうしてなのでしょう?
理由の一つは、3人にとって編み物は、生活の中に当たり前にあったことが挙げられます。
そのことに気づいたのは、蜂が昔のビデオを整理していたときのことでした。
ビデオ映像の中に、現在3人の編み物会と、まったく同じ光景を発見したのです。
それは、伊都が50代、平次が20代、蜂が2歳のころ。
2歳の蜂は、ソファに座る平次の足元に座って、黄色い毛糸で遊んでいました。
その黄色い毛糸で、うら若き平次はセーターを編んでいました。
平次の隣に座っていた伊都が、平次に編み方を陽気に教えていたのです。
伊都の手編みの歴史
現在も伊都は、二人に編み物を教えています。
どうして伊都は、毛糸の編み方を教えることができるのでしょう?
それは遡ること、伊都が小学三年生、第二次世界大戦が始まる2年前のこと。
伊都は母である美都と、夜な夜な練炭火鉢を囲んで過ごしていました。
テレビはなく、美都は夕食後、伊都のためにセーターをいつも編んでいました。
当時は既製品の服はほとんどありません。
毛糸だけを売る店があり、そこで毛糸を買って、
家庭でセーターやカーディガンを編む時代です。
毛糸を編むことは、家庭の衣服を整える必須の技術でした。
そんな時代に、伊都は、美都が編み物をする姿を見て育ったのです。
幼い伊都は、美都がどうやってセーター編むのかに興味を持ち、手の動きをよく見ていました。
いらない毛糸をもらっては、
ガーター編み、メリヤス編み、かのこ編みで10cm四方を編む模様の基礎練習や、
編み始めの目の作り方(毛糸の持ち方)など、編み物の基礎を細かく美都に習いました。
やがて伊都は、10cm幅のマフラーを編むようになります。
このあたりから女の子の楽しみといいますか、伊都のものづくりの楽しみが膨らんでいきました。
伊都にとって、宿題がない日に模様編みの基礎を練習することは、とても楽しいもので、
近くに美都がいて、セーターが少しずつ編み上げていくのを見るのも、とてもわくわくするものでした。
伊都の母の手編み生活
一方で、美都の編み物生活はどんな様子だったのでしょう?
美都は伊都が学校に行っている日中に、隣三軒ご近所の奥さんと集まっては、
一緒にラジオを聴いたり、雑誌「主婦之友」を開いて、
「こんな形のセーターも素敵ねえ」とおしゃべりをしたりしながら、
子どもたちの洋服を編んでいました。
頻繁ではなくとも、編み物が好きな友達と集まって、
「どんなものができた?」と見せ合ったり、
「こうしたらいいねえ」と話したりしながら編むのが、
一人で編むよりもずっと楽しかったのです。
幼い伊都が学校から帰ってくると、
「よしこちゃんがかわいいセーターを着ていたから、私にも作って」と美都にせがむことがありました。
美都は、伊都が願ったものを実際に作り出してくれたのです。
ものづくりの喜び
そうした幼少期を過ごした伊都は大人になり、やがて結婚し、子どもが生まれ、子どもたちにセーターを編むときを迎えます。
時は戦後を迎え、編み物の本も、毛糸も、自由に手に入る時代になりました。
伊都は美都のもとで基礎を学んでいたので、
本を見ながら「自分だったらこんなのを作りたいなぁ」と思い描き、
試行錯誤しながら、想像したものを作ることができるようになりました。
時には自分のセーターをほどいで、
赤ん坊だった平次やその兄弟のための服に、編み変えたりもしました。
毛糸は、編み変えることができ、次の作品、次の人へ受け継がれていきます。
同じように、編み物をする環境や習慣も、
美都から幼き伊都、そして現在の3人へと受け継がれてきたのです。
現在の伊都も、夕食後よく編み物をしています。
家の感覚、鍛えられた母性
戦前とは違い、本だけでなく、テレビ番組やデジタルコンテンツといった、豊富な娯楽がたくさんある現代でも、
編み物が続いているもう一つの理由は何でしょう?
それは、編み物をしている人の周りにできる、妙に落ち着く雰囲気が好きだからかもしれません。
編み物をされる方や、周りにしている人がいる方にお尋ねしたいのですが、
編み物をしていると、周りの人が落ち着いたり、
自分が編み物をする人の近くにいると、落ち着いたりした経験はありませんか。
編み物を黙々としている伊都のそばにいると、蜂は妙に落ち着く体験を何度もしています。
まるで、ざわついていた心の水面が、すーっと鎮まるかのように。
テレビの音が鳴っていても、伊都と言葉を交わさなくても。
この感覚は何なのだろうと、蜂はずっと不思議に思っていました。
蜂自身が編み物をしているとき、こんなこともありました。
テレビの音が鳴っていても、言葉を交わしていなくても、
蜂の兄弟が部屋を見渡して、「こういうのいいねぇ」と一言、満たされたような顔で言ったのです。
このとき蜂は、
”あぁやっぱり…。毛糸を編む人の周りには、人を落ち着かせる雰囲気ができるんだ…”
と感じました。
こうしたとき、一体何が起こっているのでしょう?
不思議がピークに達した蜂が、伊都に「何が起きていると思う?」と尋ねると、伊都は間を置かず、静かにこう言いました。
「本当の家族の雰囲気っていうんかねぇ。温かみというんかねぇ、ざわざわしていない。そんなのかもわからないねぇ。」と。
ざわざわしていない、家族の”本当の”温かみ。
”本当の”家族の雰囲気。
(本当の家族には人それぞれのイメージや感覚があると思います。
そのためここでは、「私たちが感じている」という意味を込めて、かっこつきの”本当の”としています。)
このとき蜂は思いました。
“やっぱり…。
私たち三人が長い間、繰り返し問いかけられていて、薄々感じていたけれど、はっきり気づいていなかったこと…。
それは、鍛えられた母性というテーマなんだ…。
それをもっと深く理解して、意識的に生み出せるようになることなんだ。
ビデオが撮影されたあのときも、現在も、ずっとそのテーマは近くにあって、
もしかすると、気づかれるのをずっと待っていたのかもしれない…。”
蜂は心の中で、何かが結晶化されていくのを感じていました。
それはビーレエションシップが始まる少し前のことでした。
糸
糸紡ぎ、機織り、刺繍に編み物は、古来からどの大陸にもあって、女性の仕事でした。
河合隼雄は、フォン・フランツの著書を引用して「糸つむぎは古来から女性の仕事のなかの重要なもののひとつとして、女性性を象徴するほどの重みをもったものである」とも述べています。
男性が狩りに行く間、子どもを育てながら女性同士が集まって、糸と針仕事をしてきたのです。
それは生活をよくするために事を成すといった、アニムス(女性の中の男性の原形)によって鍛えられた女性の姿です。
「かわいくて、ふわふわした毛糸のイメージを自分に重ねたくて、編み物をする」といった、見栄えを求め、
自分を中心にした動機で始めるものとは、特徴を異にするものです。
太古から連綿と続く女性の糸と針仕事の営みと、それがもたらす感覚は、誰に教えられずとも、人の感覚の中に宿っている気もします。
手編みの時間
蜂はこうしたことをたどるうちに、編み物をする人の周りにできる不思議な静けさと、編み物が象徴するものについて、こう考えるようになりました。
”ふわふわした温かそうな毛糸が一本出てきて、
黙々と女性の手が動き、
糸が編み目になり、
編地が出来てくる。
「今」という時間が、編み針のリズムを刻んで、編み目に変わっていく。
そうした時間とリズムが、編み物をする側にいる人にも伝わり、ざわついていた心が、すーっと整っていく。
編み手は、しばらく編んでは、腕を伸ばして、編地全体を見つめ、
どのくらいできたかを確かめる。
そばにいる家族は、その光景を見て、
家族のために編んでくれているという、ぽっと灯のともるような温かさを感じ、心に広がっていく。
昔ながらの家庭の光景。”
それは、家族の温かい雰囲気に包まれた、静かで深い変容の時間になっているのかもしれません。
そうした時間があるのも、限られた生活の中の資源から、編み物を始める手立てと、編む時間と、編むエネルギーを用意したからこそです。
編み物は、美都から幼き伊都、そして現在の3人の女性に脈々と流れ、生活の一部となっている活動です。
ものづくりの喜びは時代を越えても不滅で、この楽しみのために、現在の伊都・平次・蜂の3人も編み物会で集まっています。
その活動が示していたテーマは、暮らしを育もうとする鍛えられた母性と、それによってもたらされる静かな家族の温かみなのかもしれません。
そうした感覚が、自分たちの生活からも、それを望む人の心からも消えてほしくない。
こうした経緯で、3人はビーレエションシップのテーマにたどり着いたのです。
引用参考文献:河合隼雄(1994)「昔話の深層 ユング心理学とグリム童話」講談社+α文庫