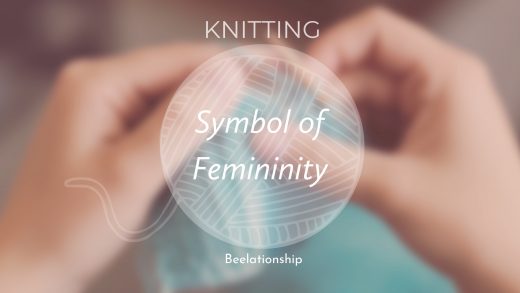伊都の刺繍との出合い
伊都は幼い頃に母の美都の影響で毛糸と出会って以来、家庭では毛糸一筋でした。
そんな伊都が50代のある日、洋裁職人として勤めていた職場で刺繍と出合います。
きっかけはささいなもので、洋服の裏地となる白い布を裁った残りが職場にたくさんあったから。
職場には手仕事が上手な人が集まっていて、ある洋裁職人は小学生の子どもの靴袋を作り、またある洋裁職人は生まれたばかりの孫のために小さな刺繍をしたりと、残った白い布を使って縫い物をすることが広がっていました。
伊都はそんな環境の中で、ひときわ刺繍に興味をひかれました。
布はすぐそこにあるし、刺繍糸はひとかせ90円と家計の負担にならないしと、気軽な気持ちで刺繍を始めたのです。
初めは本を見ながら、簡単なバックステッチ刺繍をしていました。
しかしもとは細かな作業が得意な伊都のこと。
どんどん刺繍が面白くなります。
そしてあるとき同僚に刺繍教室の存在を教えてもらい、本格的に刺繍を習うようになります。
こうして伊都の刺繍は始まったのです。
伊都が刺繍を辞めた理由
伊都は刺繍に出合って以来、暮らしの中で時間を作っては、編み物と刺繍を交互にする生活を続けてきました。
ところが80代を迎えた頃、目が見えにくくなったことと体調の不安から、針を持たなくなってしまいました。
幼い頃から触り続けていた糸を片づけ始めたのです。
大事にしてきたことに蓋をして遠ざかろうとすると、まるで糸の切れた凧のような心境になることがあります。
あのころのような張り合いを取り戻したいと思っても、何かをする力がわいてこない。
やじろべえのように両極に気持ちが揺れ動きながら、やがてたどり着く心境は、
「なんのために生きているんだろう…。」
今ならわかるのですが、こういうときは力を無理に出そうとしなくていいのだと思います。
この時に必要なことは、例えば刺繍をすることではなくて、なにもせずに力を抜くこと。
案外その中に次の一歩が待っているものです。
でも渦中に入ると、なかなかそうは思えません。
伊都もそうで、これまで自分がつくってきたものに価値を見出せず、これから何ができるのかも見えない、真っ暗の中にいるように感じていました。
伊都がときどき「刺繍作品はかさばるだけで、何になるんかねぇ」と言いながら肩を落とすのを平次と蜂が見ると、二人は悲しくてたまりませんでした。
しかし二人はこの言葉を聞いて、伊都の刺繍作品をなんらかの形にまとめられないかと話していました。
もしかするとそれが伊都が自然に次の何かにたどりつく支えになるかもしれない。
そう思った二人は、「個展を開く?本にまとめる?」などとアイディアを出してきましたが、
時と場所を選ばず、恒久的に刺繍作品を見てもらえるような場にしたいという思いがあったことと、
伊都の刺繍作品の中には本を参考にして刺されたものもあるため、全てがオリジナル作品ではないという点で、なかなか話がまとまりません。
三人三様にもんもんとして、突き抜けられないガラスの天井を感じている時期が数年続きました。
伊都の過去の作品に光を当てる
そんなときに迎えた、2015年12月31日。
蜂はなんとなくこぎん刺しがしたくなったことと、伊都に刺繍の温かみをプレゼントしたい思いから、
伊都の誕生日プレゼントにこぎん刺しを作って贈ることにしました。
ところが蜂はあまり色のセンスがなく、伊都の部屋においてもなじむ色が決められず困ります。
そこで伊都に作ってもらったバッグなどの刺繍作品を客観的に見て、伊都の好きな色を見つけ出そうと、
写真をひと作品ずつ撮り始めていました。
そのとき。
ピッカーン!
蜂の頭の中に高速の光が駆け抜けました。
その高速の光の中には、
伊都の刺繍作品の写真一枚一枚が繋がって流れるように動き、上のビデオが出来上がる様子があったのです。
その光は、これが、いつか平次と話していた、伊都の刺繍作品をまとめる形だよ!と見せてくれているようにも思えました。
イメージが見えてきたら、あとは動くだけです。
全ての伊都の刺繍作品を網羅するため、ひと作品ずつ写真を撮るのです。
刺繍作品を一枚写真に撮ると、他の作品があることを思い出して次にそれを撮るといったことが、嵐のように繰り返されました。
その嵐は蜂の家だけでなく、伊都の家の納戸にまで至りました。
そこで発見したのは、まだ額装されずに隅に丸められていた刺繍作品…なんていうこともありました。
あぁ、なんともったいない。
膝が痛む伊都もつられてよいしょと立ち上がり、
他の隠れている刺繍作品がないかと納戸の隅々まで分け入り、二人でセッティングしながら写真に収めました。
伊都の体はまだきついときでしたが、伊都は時折いきいきとした表情を見せるようになっていました。
蜂はそのときふと不思議な気持ちになりました。
作品のひとつひとつに当時の伊都がいる…作品のひとつひとつに伊都の思いがある…。
そのとき蜂は伊都と一緒に、伊都の半生を旅していたのでしょう。
そこで蜂は、伊都自身の声で、刺繍作品の背景と思いをビデオに吹き込んでもらうことを思いつきます。
それは平次と蜂が、ずっと聞きたいけれど聞いていないことでもありました。
こうしてビデオの音声は、蜂が伊都に作品の背景や思いを聴く形式となりました。
二人で話すことで感情の抑揚や方言が入り、二人の性格も現れているような気がしてお恥ずかしいですが、どうかご容赦ください。
またナレーション部分では、蜂は聞きやすい声で読むのことがうまくなかったため、
声の仕事をしていた平次に発声の訓練を受けました。
深い部分での相互作用が起こる
3人の女性が、ビデオが出来上がって気づいたことがあります。
1つ目は、気落ちしていたり体調が優れないときでも、そのときその人が感じることの中に、
何がその人にとって支えとなるのかという指針があるということです。
伊都の場合は、“こんなものが何になるのか。無駄なものでしかない”という気持ちの中に、次へのヒントが隠れていたのです。
実際にこれまでの刺繍作品は無駄なものだったのでしょうか?
とんでもない!その作品のなかに、伊都らしさが詰まっていて、気づかれて花開くときを長い間待ちわびていたのです。
作品に隠れていた伊都らしさに気づいたとき、伊都は自分の次の道を自ら見つけ出したのです。
2つ目は、起きている流れにひたすら沿うことで、それに関係した人に変化が起きたことです。
伊都の刺繍作品のビデオが出来上がる節目節目で、不思議なことに、伊都の体調に変化が起きたのです。
ビデオの概観ができたときの伊都は、変わらず針を持たなくなったままで、糸も片づけてしまっていました。
ところが映像にナレーションを吹き込み終わったとき、伊都に「針をもっと大事にしなさい」と言われているかのような出来事が起きます。
伊都は気づいたことを大切にし、これまでのような完成度ではなくても、
できる範囲で刺繍をやってみようと思うようになりました。
そして久しぶりに刺繍布を買い、オリジナル作品第2弾に取り掛かり始めたのです。
ところがそれも順調にいったわけではなく、やはり目が見えにくいことは残っており、
オリジナル作品第2弾の製作を止めてしまいます。
伊都はそれまでにも目の手術をしてよく見えるようにしたいと願っていて、長い時間が経っていましたが、
他の体調が思わしくなかったことと、手術までして刺繍をする必要があるのかと決めかねていたのです。
そんな頃、離れて暮らしている蜂が撮り忘れていた伊都の刺繍作品を思い出して、ビデオに追加すると、
そんなことは知らないはずの伊都の心の迷いがすっと晴れ、体調も落ち着き、目の手術を受けられることになります。
やがて手術後の安静期を越えると、伊都はついにオリジナル作品第2弾をやり遂げたのです。
そして伊都がビデオの会話の録音に加わり、蜂がビデオの日本語字幕と英語字幕を完成させた頃、伊都は新たに刺繍布を買いました。
現在は刺繍のバッグを作るという計画があるようです。
好きな図柄を眺め、まるで少女のように、それはそれは楽しそうに大きさや色を検討しています。
もう迷わずに前に向かって進むと言っています。
このように指針を軸に動いていると、あちらこちらでぽつんぽつんと点のように変化が起こり、やがてその変化同士がつながって、変化が立体的になるという体験をしました。
蜂にとっては、その人の歴史や現在のあるがままの流れを一緒にたどるうちに、
その人の中から次に何をするかという答えが自然に出てくることを信じていましたが、
伊都にビデオの会話に加わるようにしたことで、伊都がこんなにも元気になるとは想像していませんでした。
その人の歴史を一緒にたどることは、現れようとしている命の源ともいえる流れとその人自身をしっかりとつなげることで、
ひいては、内側からエネルギーを燃やして生きていく再出発を支えることになるということを実感しました。
それはとてもシンプルで、無理がなく、持続可能な方法のようです。
叶えたい願いにじっと耳を傾け、辛抱を辛抱と感じずに寄り添い、共に限界を超える方法を探す中で、
蜂自身の心の器も少しばかり広がるように、作り直されている感覚を覚えました。
このように点と点の変化が立体的な変化になると、
伊都と蜂は、たとえ物理的にすぐ隣にいなくても、共有している流れに芯から心が満たされ、
自然と元気が湧いてくるのを感じるようになっています。
それはまるで枯渇することのない元気の源という温泉に二人で入っているかのようです。
ビデオはこうして出来上がり、伊都の刺繍作品を記録したものにとどまらず、
こうした一連の流れを声を通じて、思いがけずとらえたものにもなっています。
さらにビデオの番外編には、録音風景の舞台裏が収録されています。(ここで聞こえてくる伊都の弾んだ声は、本当に久しぶりのことでした。)
皆様にも楽しんでいただけたら嬉しいです。